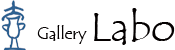世の中のやきもの愛好者の数が、これほど絶滅危惧的に少なくなったのは、愛好者の皆様が「この土味は堪まらんなぁ」「この高台土見せはいい味出ている」などと言うものですから、それを聞いた初心の人が、やきものなどに首を突っ込んで土を食べ続けているとミミズ男になってしまうのだ、と固く信じてしまうからです。
そんなときにはぜひ教えてあげてください。
ミミズ男になったのはやきもののせいではなく、前世の因果によるものであること、そしてミミズ男になってもけっこう楽しく暮らしていけるのだ、ということを。
いやそれよりも、これらの話はべつに土を食った感想を述べているのではなく、「土味」とは土の質感と焼き色とを合わせた視覚的表現なのだ、ということを教えた方がよりわかりやすいかと思います。
この「土味」という言葉は、備前のやきものについて語られるとき最も多用されます。
他の焼締め陶に比べて、「土味」が登場する回数は圧倒的に多いのです。
不思議なことですね。
信楽や常滑、越前、丹波など他の焼締め陶においても、その焼け肌が重要な要素として問われることに変わりはありません。
ですがこれらは、なぜか「土味」という言葉よりも「見事な焼け」、「良い焼き」、「素晴らしい土肌」などといった直截的な表現で語られることが多いのです。
「土味」は別に岡山地方の方言ではありません。この謎を解く鍵は原料である「備前の陶土」の性質にあります。
「備前の土」の特殊性は、焼成中の炭素とアルカリに対する、過剰で独特な反応のし方です。
全国各地に「一見似たような土」はいろいろあるのですが、熱反応を経て「備前焼」になるやきものの素地は、「備前の土」だけなのです。
陶商や愛好者達は、備前のやきものを「窯変もの」や「土味もの」と呼んで大別しています。
前者は灰被りやサンギリなどと呼ばれる、焼成中の付加物によるペインティング効果で彩られたものです。
そして後者は土の焼け肌そのものが充分鑑賞の対象となり得るものを呼びます。
「窯変もの」の方が派手でコントラストも立ち、色も多いので一般受けし易く人気もあり、値段も高額に設定する業者や作者も多いのですが、一見地味で激しい変化もなく、一歩間違えばただの生焼けとも見られかねない「土味もの」は、長年本気でやきものに関わっている者達から熱烈に支持される、いわゆる「玄人受け」するやきものです。
焼きあがった土肌が絶妙な「土味の良い」ものをみていると、やきものに関っていて本当によかったとしみじみ幸福感を覚えるものです。
ただ、残念なことにそういったものには、そう簡単にお目に掛かることができないのです。
なぜならば「単なる土の焼死体」と「特上の生々しい土味」とは紙一重であり実作においてのストライクゾーンは極めて狭く、限りなくピンポイントに近いのです。
小出尚永氏は近作においてこの「本当に良い格別の土肌」に照準を合わせています。
素晴らしいことです。
名匠原田拾六氏のもとで14年間の研鑽を積んだ小出氏は独立後の初窯ですでに完成度の高い作品群を世に出してきました。
原田氏を正しく継承した焼成と造形(これは人が考える以上に難易度の高いことなのです)に加え独自の感覚がみられる金属器由来の鋭利な作風と幅を持たせた上で、リスクの高い「土肌一発勝負」ものに挑戦する姿には拍手を送らずにはいられません。
そして、それらを裏付ける土作りから焼成までの構想、そして構築を支える強い意志が小出尚永氏の最大の強みなのです。
今回の作品に当方が自信をもてるのは、酒器という限られた器種のなかで、小出氏の様々な側面が確実に現れた佳品をそれぞれ揃えてご紹介できたことです。
ここで述べた「土肌一発」の作品も2点紹介しています。画像ではこの土の良さを充分にお伝えすることは適わないでしょうが、興味を覚えて下さった方には是非ともお勧めしたい逸品です。
それでは、「新やきもの通信Vol.2 小出尚永の酒器」をどうぞご覧下さい。